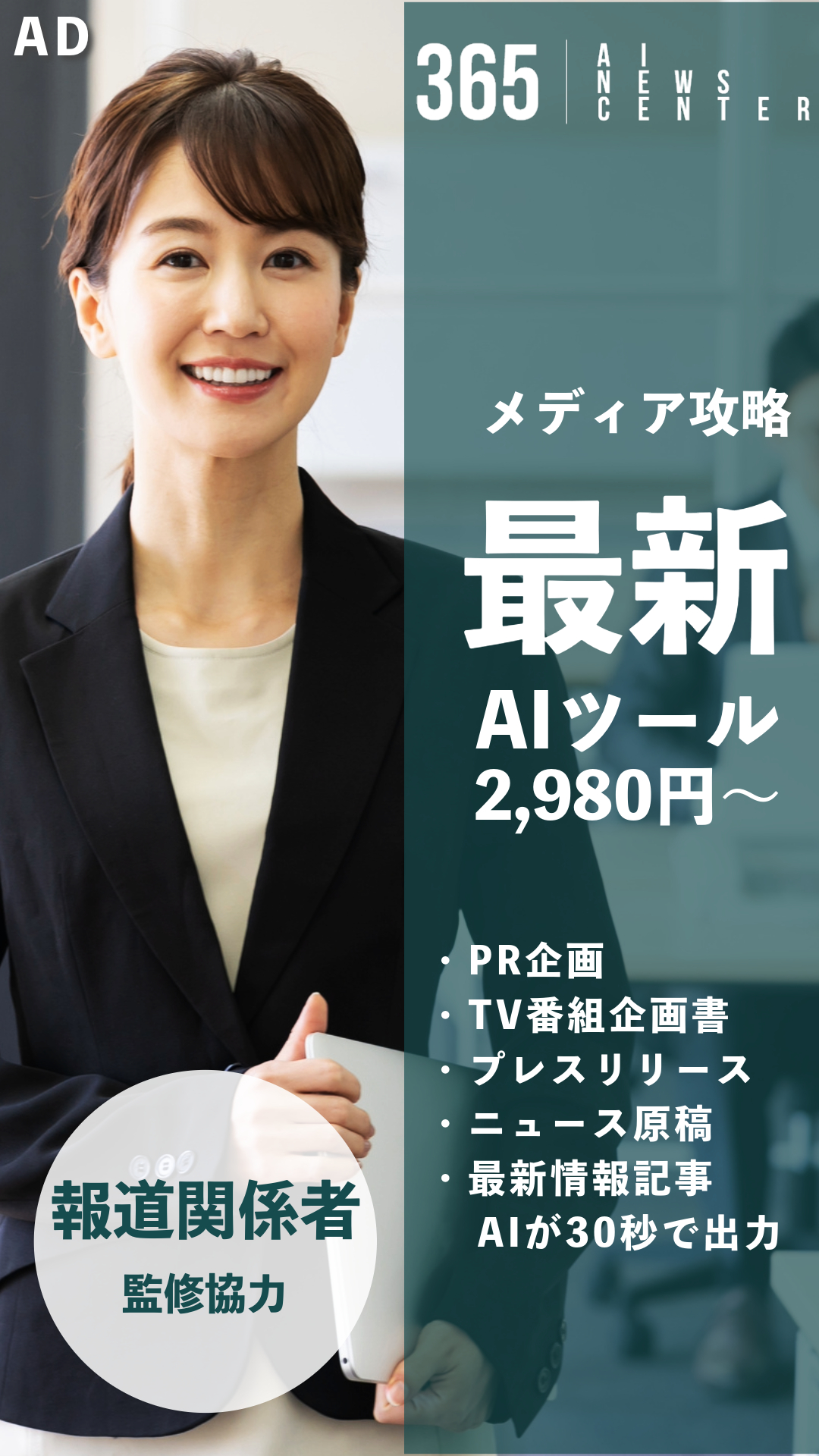携帯電話大手3社による値上げの波が、格安ブランドにまで及んでいる。ソフトバンクは9月25日から子会社のワイモバイルで新料金プラン「シンプル3」を導入し、実質的な値上げに踏み切る。
各メディアも報じているが、これまで政府主導で進められてきた携帯料金の値下げ競争が、ここにきて一転。NTTドコモやKDDIも今春から順次、料金プランの改定を実施している。新プラン「シンプル3」は、データ容量に応じてS(5GB)、M(30GB)、L(35GB)の3種類が用意される。現行プランと比較すると、多くのユーザーにとって月額料金の実質的な負担増となる見込みだ。
SNS上では「結局、安くなった分を取り返しているだけ」「電気代も上がって、もう家計が限界」といった批判的な声が相次いでいる。一方で、「5G網の整備には投資が必要。値上げはある程度やむを得ない」との理解を示す意見も見られる。
携帯電話料金は、菅政権時代に値下げ要請を受けて大幅な引き下げが実現。しかし、通信事業者の収益性低下や設備投資負担の増加を背景に、業界関係者の間では「これ以上の値下げは困難」との見方が強まっていた。今回の値上げについて、消費者団体からは「物価高が続く中での値上げは、家計への打撃が大きい」との懸念の声が上がっている。通信コンサルタントの意見では、今後も通信各社による段階的な値上げの可能性は否定できないとしている。
一般のユーザーからは「他社への乗り換えを検討したいが、結局どこも値上げするなら意味がない」といった諦めの声も。携帯料金の家計負担増が避けられない状況の中、より賢明な料金プランの選択が求められている。
文/進藤昭仁