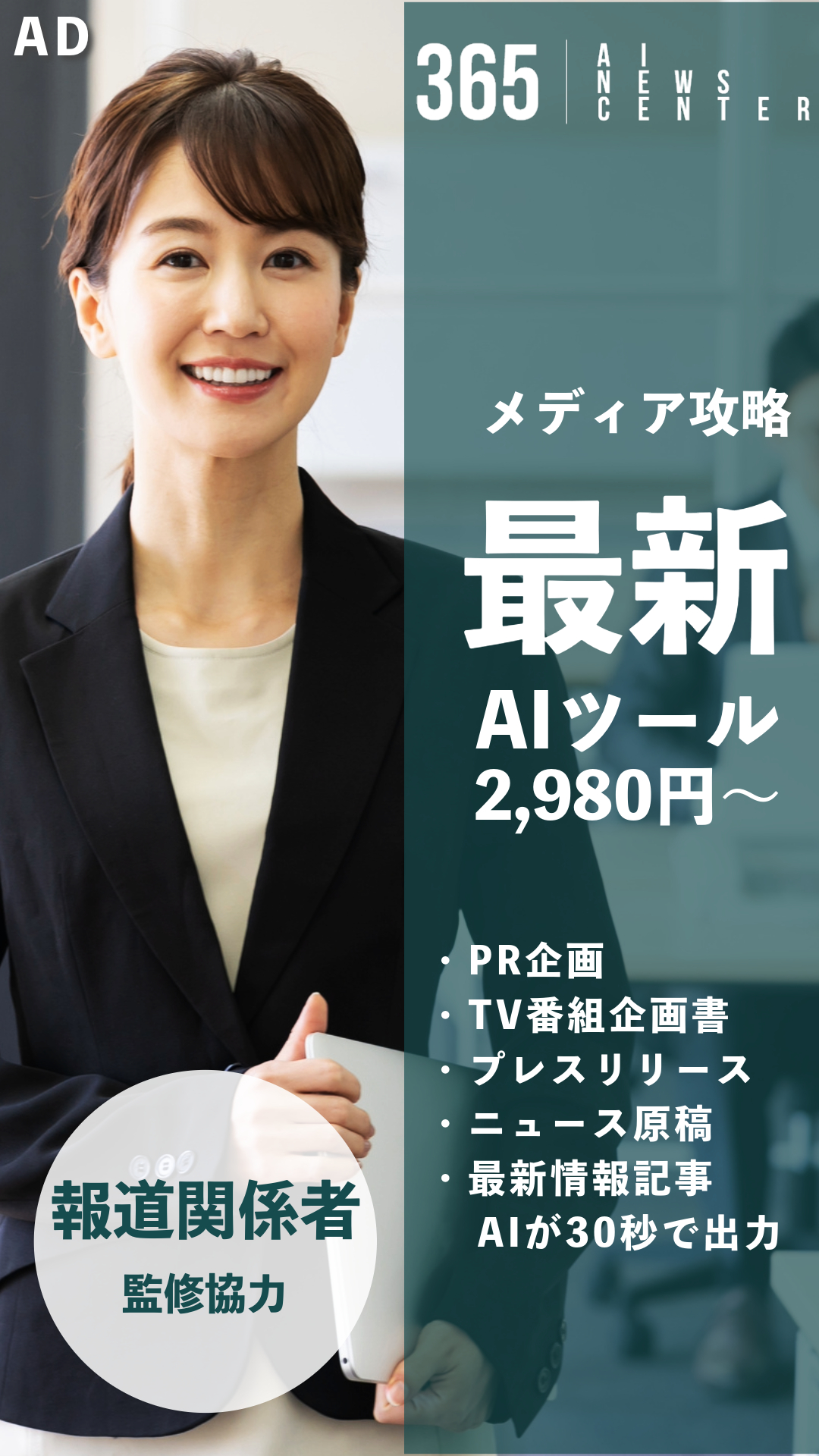警察の公式ウェブサイトを装った偽サイトが全国各地で次々と発見され、新たな特殊詐欺の温床として深刻な問題となっている。北海道警、警視庁、大阪府警など、各地の警察組織を装った偽サイトが確認されており、サイバーセキュリティ専門家からは警戒を促す声が上がっている。
特に注目すべきは、スマートフォン利用者を標的とした手口だ。画面サイズの制限により、URLの完全な確認が困難なスマートフォンユーザーが、偽サイトの被害に遭いやすい傾向にある。
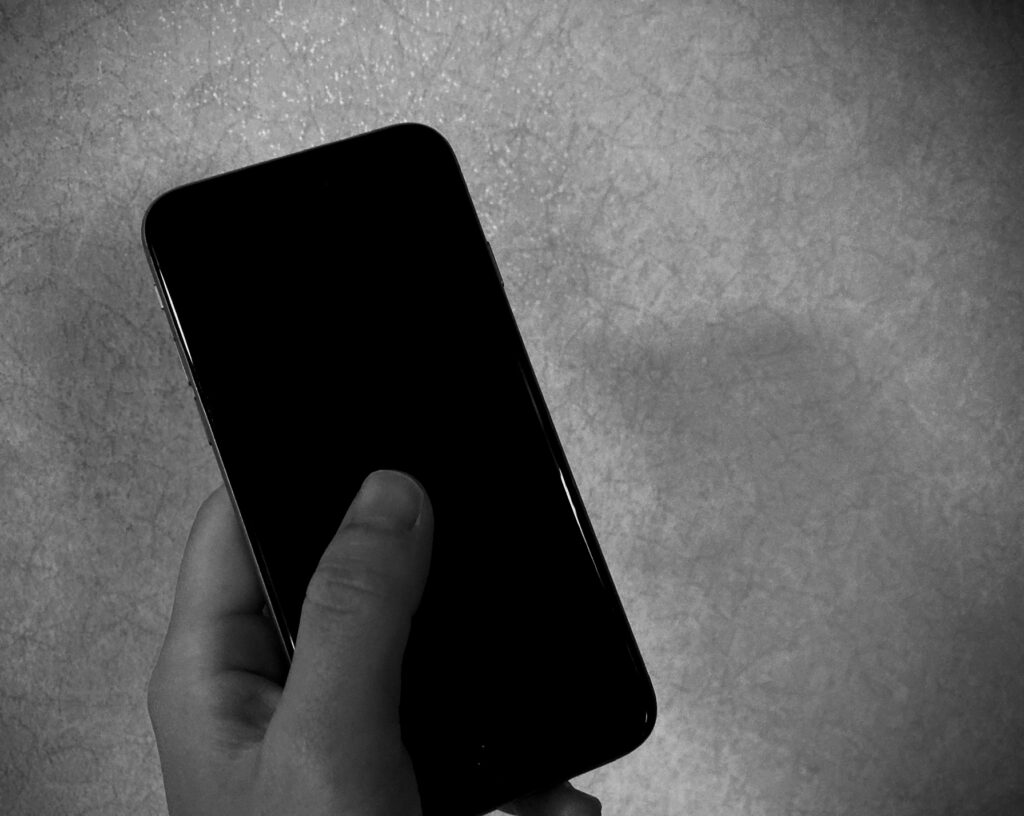
SNS上では「警察を名乗られると、つい焦ってしまう」「本物のサイトと見分けがつかない」といった声が相次いでいる。専門家によると、「警察」という権威への無意識の畏怖が、利用者の冷静な判断力を奪う大きな要因となっているという。
捜査関係者によれば、これらの偽サイトは特定のターゲットに向けて一時的に開設され、短期間で消滅する特徴があるため、摘発や削除が困難を極めている。また、サイトの精巧さは年々増しており、警察組織のロゴや書式を完璧に模倣するケースも報告されている。
「反マネーロンダリング」「口座情報の確認」といった専門的な用語を巧みに使用し、信頼性を装う手口も確認されている。セキュリティ企業の分析では、これらの偽サイトの多くが海外のサーバーを経由して運営されており、追跡を困難にしているとのことだ。
対策として最も効果的なのは、「他言無用」と言われても誰かに相談することである。第三者の視点が入ることで冷静な判断が可能になり、被害を未然に防げる可能性が高まる。また、警察組織から電話やメールで連絡が来ることは原則としてないため、そうした連絡自体を疑う姿勢が重要である。
文/進藤昭仁