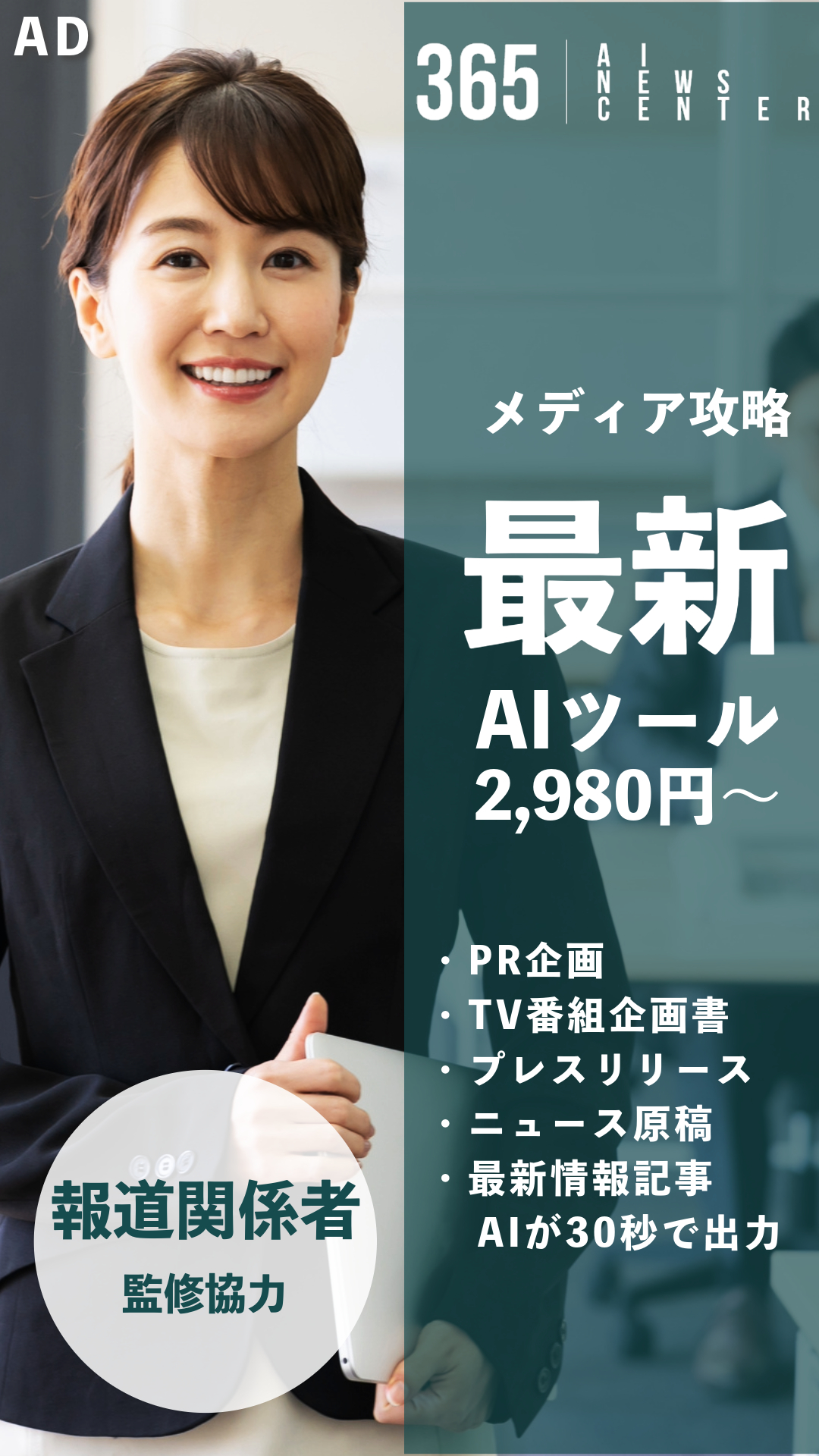外食大手ワタミとスキマバイトサービス「タイミー」が今年4月に手を組み、画期的な店舗運営モデルを始めた。サブウェイの新店舗を舞台に、店長と正社員以外のスタッフを全員タイミーワーカーで構成する「フルタイミー」という仕組みだ。深刻な人手不足に悩む外食業界の救世主となるのか、それとも新たな問題を生み出すのか。SNS上では様々な意見が飛び交っている。
サブウェイ ヨコハマベイサイド本店で試験的に導入されたこの取り組み。従来の固定シフトのアルバイト中心体制とは異なり、シフトの組み方次第で短時間で働くワーカーを組み合わせる柔軟な運営が特徴だ。将来的にはタイミーワーカーから正社員登用も視野に入れているという。

この新たな試みに対し、SNS上では賛否両論の声が上がっている。
「サブウェイって種類多いし複雑だよね。スキマバイトの人が対応できるの?」
確かにサブウェイは注文プロセスが独特で、パンの種類や具材の組み合わせなど、覚えることが多い。短期間で入れ替わるスタッフが中心となる環境で、サービスの質が保てるのかという懸念は当然だろう。ワタミ側は具体的な教育方法について詳細を明かしていないが、デジタル技術を活用した作業支援システムなどが必要になるのではないだろうか。
一方で、こんな声もある。
「結局、人をコストとしか見ていない証拠じゃないか」
この背景には、雇用の安定性よりも人件費削減を優先しているのではという不信感がある。特に飲食業では、顧客との関係構築やチームワークが重要だ。経験豊富なスタッフが少なければ、サービスの質だけでなく、働く側の負担も増大するリスクがある。
しかし、新しい働き方として評価する声もある。
「自分のペースで働けるなら、むしろ歓迎。学業や副業と両立しやすそう」
多様な働き方が求められる今、時間や場所を自分で選べる仕組みは魅力的だ。また、タイミーワーカーから正社員への道筋も示されており、単なる「使い捨て」の雇用形態ではなく、キャリア形成の入口となる可能性も秘めている。
この「フルタイミー」モデルは、外食産業の人手不足という喫緊の課題に対する一つの解決策かもしれない。しかし成功の鍵を握るのは、短期ワーカーへの教育体制と職場環境の整備だろう。単に人を集めるだけでなく、働く人の成長と顧客満足を両立させられるか。
ワタミとタイミーの挑戦が、日本の労働市場に新たな選択肢をもたらすのか、それとも一過性の試みに終わるのか。外食業界だけでなく、人手不足に悩む多くの業種が注目している。
執筆 / 菅原後周