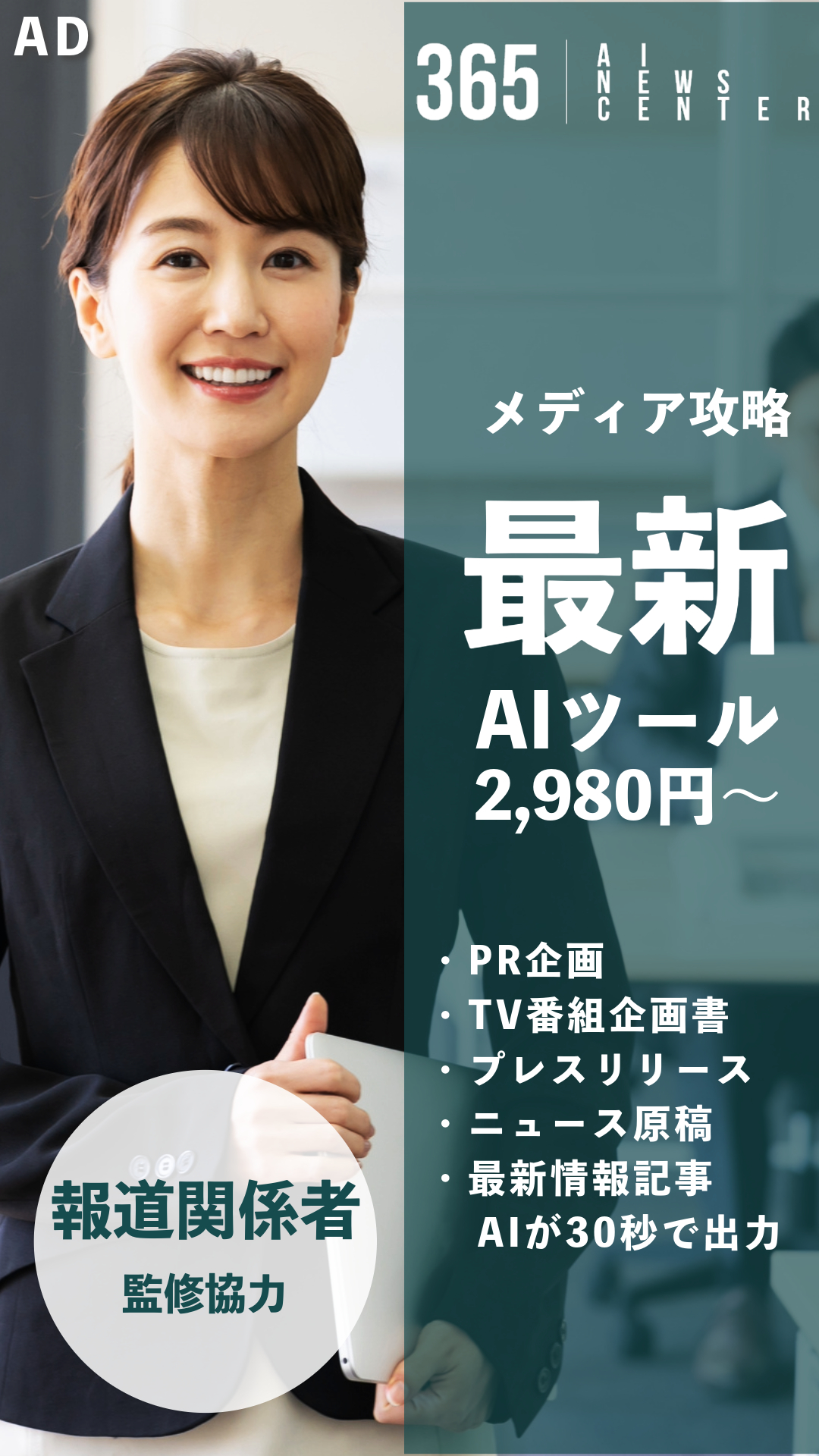愛知県豊明市が、市民全員を対象にスマートフォンなどの使用時間を1日2時間以内とすることを目指す条例案を9月に提出する方針を明らかにした。タブレットなどネット接続可能な端末も規制対象に含まれ、対象者を子どもに限定せず市民全体に広げる点で、全国でも前例のない取り組みとなる。
条例案の背景には、青少年の視力悪化や学力低下、親子間のコミュニケーション不足などへの懸念がある。しかし、SNS上では「行政による過度な介入だ」「根拠が不明確」といった批判的な意見が相次いでいる。IT評論家からは、デジタル社会において、一律の時間制限は現実的ではない。仕事でスマートフォンを多用する人も多く、むしろ生産性を下げかねないと指摘する声が多い。
2020年に香川県で制定された「ネット・ゲーム依存症対策条例」も、科学的根拠の不足を指摘され、大きな議論を呼んだ。同条例は子どもの平日のゲーム時間を1日60分以内とする目安を示したが、実効性を疑問視する声が上がっている。
豊明市の条例案も、罰則規定のない「推奨型」となる見込みだ。ある市議会関係者は「実効性よりも、デジタル機器への依存に警鐘を鳴らす意味合いが強い」と説明する。
一方、医学関係者からは「視力低下の主因はスマートフォン使用時間よりも、屋外活動の不足にある可能性が高い」との指摘もある。デジタル教育に携わる専門家からは「使用時間の制限ではなく、適切な利用方法の啓発に重点を置くべき」との意見も出ている。
市民からは「行政が個人の生活に踏み込みすぎ」「現代社会に逆行している」といった懸念の声が上がる一方、「家族でデジタル機器との付き合い方を考えるきっかけになれば」と期待する声も聞かれる。
文/進藤昭仁