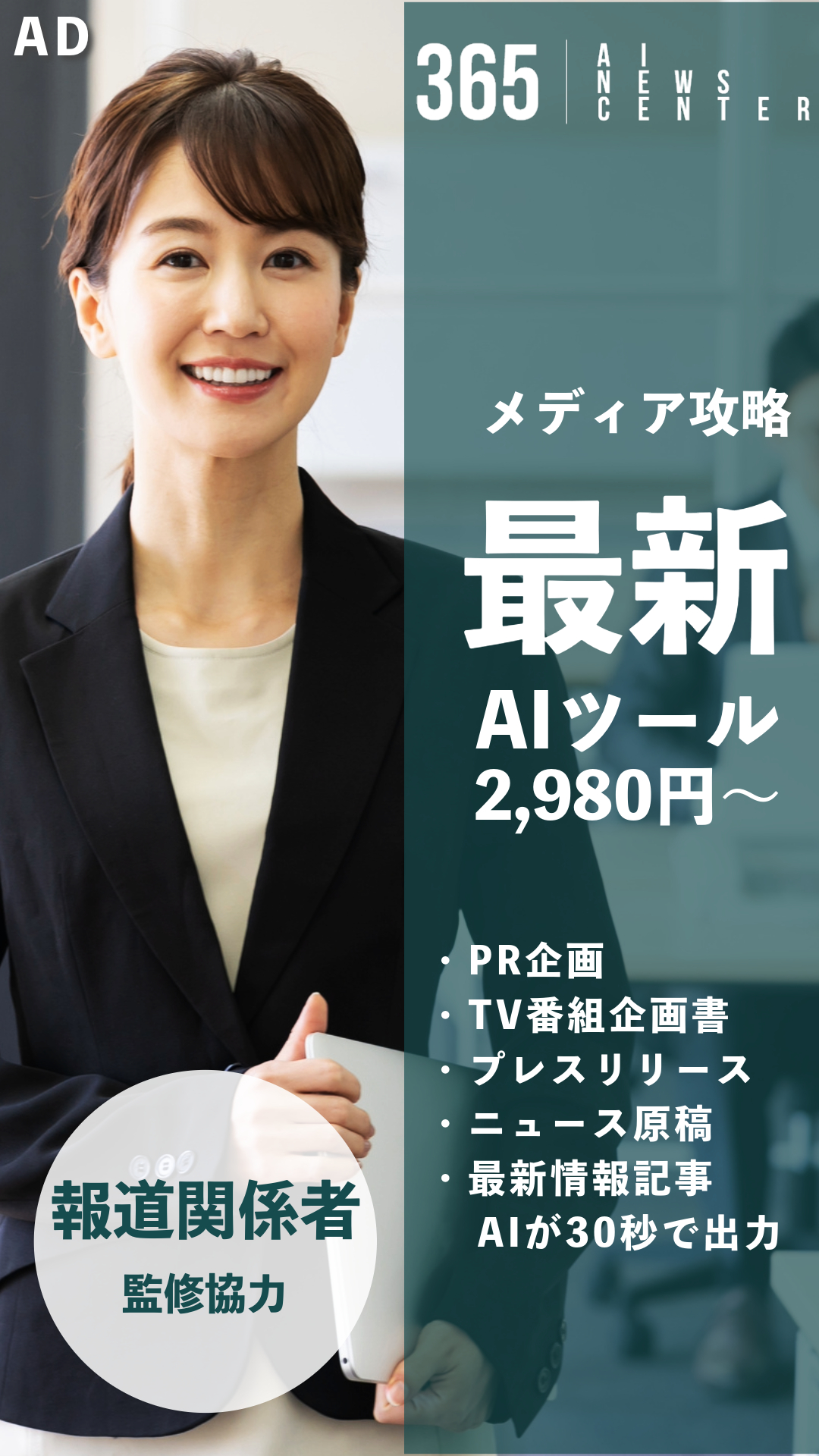総務省が発表した2024年10月1日時点の人口推計によれば、日本の総人口は約1億2380万人となり、前年より約55万人減少した。このうち日本人に限れば、約89万8000人の減少と、比較可能な1950年以降で最大の落ち込みを記録している。外国人の増加がその差を一部補っているとはいえ、13年連続で減少幅が拡大していることは、日本社会にとって見過ごせない現実である。
SNSの声と共に考える、人口減少の背景と社会的影響
SNS上でもこの発表を受けてさまざまな意見が飛び交っている。たとえば、X(旧Twitter)では「もう日本は高齢者の国になってしまった」「子育て支援が遅すぎる」といった不満の声が目立つ。一方で、「人が減ってもAIで何とかなる時代じゃないの?」「外国人にもっと頼るべきでは」といった意見もあり、社会の在り方そのものが問われている印象を受ける。
今回の減少は一時的な問題ではなく、過去10〜20年にわたって続いてきた傾向の延長線上にある。2008年をピークに総人口は下り坂をたどり、現在ではピーク時から数百万人も減少している。しかも、減っているのは若者や働く世代であり、高齢者の割合は年々増加。2024年の高齢化率は29.3%と過去最高を更新し、2050年には約37%にまで上昇すると予測されている。まさに「お年寄りの国」という表現もあながち間違いではない。
それに加え、出生率の低下も深刻だ。2022年の合計特殊出生率は1.26と、人口を維持するために必要とされる2.07を大きく下回っており、今後もこの水準はしばらく続く見通しとされている。つまり、今生まれている子どもたちは将来、少ない人数で社会全体を支えることになるのだ。
では、政府や社会はこの事態にどう向き合っているのか。少子化対策として子育て支援の拡充や働き方改革が進められてはいるものの、その効果が数字に現れていない現状を見る限り、根本的な変化には至っていないのではないか。SNSでも「保育園増やすだけじゃ意味ない」「若者の賃金が上がらなければ子どもは産めない」という意見が多く、政府の対策に対する不信感が見て取れる。
ただし、外国人の受け入れに関しては意見が分かれる。一定数の人が「外国人労働者に頼るしかない」と考えている一方で、「文化が壊れる」「治安が悪化するのでは」という不安の声も存在する。だが、長期的な人口減少が避けられない中で、労働力の確保をどうするかという視点は、避けて通れない課題だといえる。
今回の人口推計は、日本が直面する現実を改めて突きつけるものであった。長期的な視点で見れば、人口の大幅な減少と高齢化はほぼ確実に進行する。その影響は経済、教育、福祉など社会のあらゆる分野に及ぶ。
単に「人口が減っているから大変だ」と言うだけでなく、どのような社会を築いていくのか、私たち一人ひとりが考え、行動することが求められている。たとえば、地方での暮らし方を見直す、育児支援に積極的に関わる、外国人との共生を前向きにとらえる等、そうした具体的な視点が、未来の社会をより柔軟で持続可能なものにする鍵となるだろう。日本の人口問題は、単なる「統計の話」ではなく、私たちの生き方に直結したテーマだと考えてみてはどうだろうか。
文・野島カズヒコ